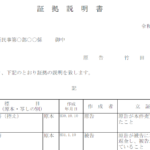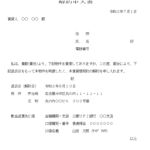簡易裁判所では、司法委員による和解の手続きが始まる!
さて、前回は、ある意味、原則的な展開を前提として説明しました。
今回は、簡易裁判所特有のポイントについて説明します。
この話は、このサイトでお伝えしたいことの中でも、とくに重要な話です。
簡易裁判所の本人訴訟が、なぜ弁護士なしでも問題ないといえるのか、というポイントについてご説明します。
前回の記事のシナリオが簡裁で行われた場合、たいてい、以下のやりとりが続きます。
裁判官 両者のご主張をお聞きしまして、司法委員の先生にもう少しお話を詳しく聞いて頂いて、話し合いで解決を検討して見てはいかがかと思います。このあと、お時間は大丈夫ですか。
原告被告 はい。
裁判官 では、司法委員の先生よろしくお願いします。
ここで、司法委員という人が登場します。
この方は、普段は、弁護士や学校の先生などの民間の方で、非常勤で裁判所の仕事をしている方です。
簡裁は、ここが最大の特色と言っても過言ではありません。
上記のように、司法委員による和解協議をすることになると、たいてい別室で、交互に話を聞いてもらい、お互いの考え方の違いを司法委員が整理し、妥協点を探り、お互いの譲歩による解決を目指すことになります。
交互に話を聞いてもらう、といいましたが、具体的には、原告が司法委員と話をしている間は、被告は待合室にて待機するというように、原告と被告が対面市内形で協議します。
司法委員による和解手続が、第1回期日から行われることによって、きわめて早期に解決できることが多いのが、簡易裁判所の大きな特徴です。
話し合いがまとまると、裁判所の和解調書という形で、合意内容を証明してくれます。
この和解調書は、判決と同様の効果があり、支払が滞納されたときは、差押えなどの強制執行までできるようになっています。
もともと、お互いが、言い分をぶつけ合った末の判決よりも、和解による解決の場合、被告側が自発的に支払をすることが多いため、強制執行の申し立ての手間や経費をかける必要がありません。
そして、仮に滞納が発生しても、和解調書があれば、差押えをすることも可能なのです。
こちらの記事(簡裁の裁判は、全然自分でできるし、すぐ終わるし、弁護士必要ないよ、という話)でも書きましたが、簡易裁判所の審理は、一般的な裁判のイメージよりも、非常に早く処理されています。その秘密の一つには、司法委員によって和解ができそうな事案は早期に和解がまとめられている、ということがあるのです。